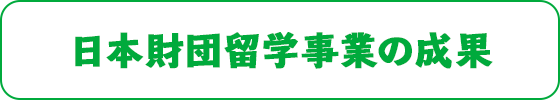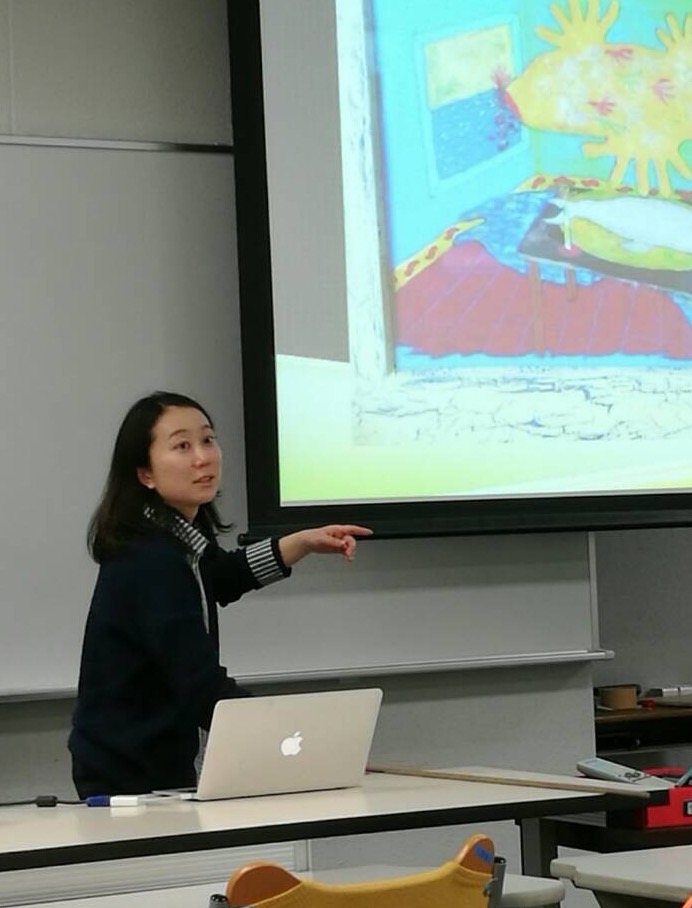
1.奨学事業による留学で学ばれた内容は何ですか。
第3期生として選出され、1年目はギャロデット大学(Gallaudet University)の国際インターンシッププログラム(International Internship Program〔当時の名称〕)の学生として1年間、英語の研修を受けました。2年目からはギャロデット大学のDepartment of ASL and Deaf Studies の大学院に入学し、Deaf Studies(ろう者学)を学びました。「デフアート」という概念に関心を持っていましたので、大学院では、欧米におけるろう者による芸術活動やデフアートが各国のろう者コミュニティや社会に与えた影響などについて研究しました。
「国際インターンシッププログラム」についてですが、現在は「国際特別生プログラム The International Special Student Program (ISSP) 」という名前に変更されているようです。当時は、インターンシップの経験を希望する留学生のために用意された特別プログラムだったようですが、当時、企業側の留学生のインターンシップの受け入れがなかなか難しい状況にあったため、名前が変更されたと聞いています。学部や専攻に関係なく、自由に様々な授業の単位を取得することができます。私の場合は、英語の研修と並行して、学部のデフアートやろう者学の入門クラスを受講しました。
2.「デフアート」という概念に関心を持ったのはいつ頃のことですか。
筑波大学で現代陶芸を専攻し、作品を制作していく中で「ろう者ならでの表現を取り入れてはどうか」という助言をいただいたのですが、当時ロールモデルと呼べる存在もおらず、「ろう者であること」「聞こえない」ことを表現することはどのような意味をもたらすのだろうかと疑問に思っていました。そこで米国から伝わった「デフアート」という概念に興味が湧き、海外におけるろう者の芸術活動はどのような状況なのか知りたいと思い、応募に至った経緯です。
3.奨学事業による留学を終えた後はすぐに帰国されたのでしょうか。
はい、すぐ帰国しました。日本の大学院を休学して留学したので、帰国後すぐに大学院に復学しなければならず、8月の終わりにカナダでのインターン・引っ越し・帰国を経て、数日後に大学院の授業開始と慌ただしい帰国でした。
4.インターンは何をされたのですか。
2010年夏の2ヶ月半間、カナダのトロントにあるろう文化センター(Deaf Culture Centre)でインターンを経験しました。「カナダろう者文化協会( Canadian Cultural Society for the Deaf (CCSD」が運営しているセンターであり、ろう児を持つ親対象のASLワークショップやアーティスト対象のワークショップなど、幼児から年配層まで様々な年代のニーズに応じたワークショップを積極的に提供する場と機能しており、また、カナダや世界中から集めたデフアートの芸術作品を展示したギャラリーも併設していました。そこでは主に展示やギャラリー・ツアーなどのアシスタントとして、ギャラリー内のガイドやギフトショップの対応の仕事に関わりました。それと並行して、カナダのろう者アーティストについて調査しました。

5.留学を終えた後、今までにどのようなお仕事・取り組みをされてきましたか。
大学院を卒業後、国立大学法人筑波技術大学障害者高等教育研究支援センターにて5年間「ろう者学教育コンテンツ開発プロジェクト」に携わりました。当時、日本においてはろう者学の教育カリキュラムがなく、指導ノウハウや指導できる人材が不足している状況でした。そこで、ろう者学の教育カリキュラムや教材を開発し、全国のろう学校や高等教育機関などに提供してきました。コンテンツ開発以外にもデフリンピック啓発、情報アクセシビリティフォーラムの映像部門、ろう女性学プロジェクトなどにも関わらせていただき、日本のろう関連の研究者や活動家、芸術家とお会いする機会に恵まれ、貴重な経験を積むことができました。米国でろう者学を学んだとはいえ、日本のろう者学やろう歴史については知識不足でしたので、そこで多くの知識を吸収できたことは自分の日本におけるろう芸術の研究にも活かされていると思います。家庭の事情により、転職・引越しを経て、今は某ろう学校の高等部で美術・デザイン教育に携わっています。私個人の活動としては、社会福祉法人トット基金の育成×手話×芸術プロジェクトの「アートを通して考える」企画にスタッフとして関わらせていただき、美術館における手話のプログラムやエデュケーター育成の意義、そして聞こえないがための表現とは何かということについて再考しています。
6.奨学事業による留学終了から現在で何年目になりますか。
2010年8月に帰国したので、早いもので今年で10年目になります。
7.その10年目、東京ではオリンピック・パラリンピックが開催されます。56年前の東京大会ではパラリンピックの名前がありませんでした。東京1964と東京2020の新旧エンブレムを比較して、管野さんはどのようなことをお感じになられますか。
東京1964のエンブレム
https://www.joc.or.jp/games/olympic/poster/1964.html
東京2020のエンブレム
https://tokyo2020.org/jp/games/emblem
1964年に開催された東京オリンピックのエンブレムは、シンプルでかつ力強さをイメージさせます。一方、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのロゴは、伝統的な市松模様を巧みに配置し、様々な人が集結する・繋がるイメージを表しています。最近LGBTに関する啓発の企画も各地で開催されているのを目にするようになりましたし、母校(大学)の障害学生支援室もダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターと名称が変更され、在学当時、支援対象となっていなかった発達障害も支援対象に加わりました。このように多様性が受容される社会に向けて、広がりを見せている日本の現状を表しているのではないでしょうか。パラリンピックの開催に伴い、障害者アートも盛り上がりを見せていますので、アートの風潮もその影響を受けてどう変化していくか楽しみにしております。
8. 「グローバル人材」という言葉があります。私はきこえないグローバル人材を次のように考えています。共生社会に求められる人材像としては、(1)きこえない日本人としてのアイデンティティを確立していること、(2)外国の手話言語を含めて異なる言語を幾つか習得していること、(3)海外の様々な人と協調関係を構築できること、(4)国際的な視野に立って社会貢献するための知識と経験を備えていることです。この4つの条件それぞれについて、管野さんご自身はどのように自己評価されますか。一つ一つお話しください。
日本では聾学校に通っていたので、ある程度ろう者のアイデンティティについて自覚していたつもりでしたが、米国の大学院で、多種多様なクラスメイトや教員に囲まれ、また留学生やアメリカ人との濃いルームシェア生活を通して、アメリカ手話言語が第一言語という環境のもと、毎日直接深い議論を交わしていく中で、より日本人ろう者としてのアイデンティティが強固なものになったと思います。ただ、(3)海外の様々な人との協調関係については、残念ながら現在の職場では果たせていませんが、アートの現場もグローバル化してきていますので、個人の活動として海外のろう芸術関係者との協調関係を構築・継続し、貢献していきたいと考えております。
9. 「より日本人ろう者としてのアイデンティティが強固なものになった」の具体例を教えてください。
色々ありますが…わかりやすい例としては、大学院で手話語りや手話ポエムなどの手話リテラシーの授業を受講し、その上、ギャロデット大学や地域で開催される手話語りのイベントに参加する機会があり、そこで繰り出される手話の美しさに心奪われ、感動しましたが、何故かどこかでしっくり来ない自分がいました。内容の理解はもちろんできますが、自分にとって第二言語だったからかもしれません。日本に帰国後、手話語りのイベントに初めて参加し、そこでまた違う感動を味わい、懐かしい故郷に帰ってきたような安心感を感じました。そういう意味では、自分は日本人ろう者であると自覚したきっかけの1つであったとも言えます。
10. 管野さんが専門とする芸術の分野で「デフアート」のあり方が議論されていますが、これらを含めて日米の大学院で学んだ事柄を、教員としてきこえない生徒に美術を指導する中で、どのような形で活かせていますか。具体例も教えてください。
今の職場ではデザインの授業が中心のため、なかなかデフアートについて直接教える機会はなく、まだ模索中ですが、様々なロールモデルに触れる機会を与えるようにしています。ろう芸術の研究をしていく中で、様々なアーティストに会ってきましたが、デフアートと名付けられることを好まないアーティストもいますし、ろう者であることを強く主張するアーティストもいます。そのスタイルに良し悪しはありません。大学時代の恩師から学んだ姿勢の1つですが、様々な参考例を見せ、助言することもありますが、こうであるべきだと押し付けるようなことはせず、生徒の考えやアイデアを尊重し、そこから膨らませるようにしています。
11. では、管野さんが日米の大学院で学んだ事柄を、個人的な活動でアートの現場に関わる中で、どのような形で活かせていますか。具体例も教えてください。
日本でよく質問されるのは、デフアートの定義です。一応、米国の例を説明しますが、日本においては先行研究もごくわずかで、福祉分野あるいは障害者アートに含まれている見方が強いと思います。米国でも一般の人々に受け入れられているかといったら、そうではありません。これまで様々な専門家やアーティストにお会いする機会に恵まれ、デフアートの社会における位置付けや役割、ろう芸術の発展やその芸術活動を支える環境整備の在り方などについて議論を深めていく中で、米国で学んだことは活かされていると思います。帰国直後はデフアートを広めたいという気持ちが強かったのですが、最近はデフアートという用語に拘らず、耳が聞こえないがために研ぎ澄まされる感性やそこから生まれる表現に興味をもち、アートを通して多くの人々にろう者の存在を認知してもらうためにはどうすれば良いのかということを考えるようになりました。
米国から入ってきた「デフアート」の概念に関心を持ったことから米国留学を実現し、そして帰国後はきこえない子どもや大人が持つ感性の表現を、学校教育現場や個人的な活動の中で大事にしていく、そんな姿勢が伝わってきます。東京2020の開催で日本の社会はさらにグローバル化していくでしょう。管野さんも頑張ってください。
参考文献
- 日本財団聴覚障害者海外奨学金事業10周年記念報告誌(非売品)に掲載された、管野奈津美「『聞こえない』芸術表現の可能性を模索して」
- ろう者学教育コンテンツ開発プロジェクト https://www.deafstudies.jp/
- 管野奈津美、大杉豊、 小林洋子、 戸井有希「ろう者学教育コンテンツの開発と共同利用の展望」『筑波技術大学テクノレポート』2014年, 22巻 (1) p.16-20
https://www.tsukuba-tech.ac.jp/repo/dspace/bitstream/10460/1269/5/Tec22_1_04.pdf - 管野奈津美、大杉豊、小林洋子「日本におけるろう芸術の動向」『筑波技術大学テクノレポート』2016年, 24巻(1) p.27-3
https://www.tsukuba-tech.ac.jp/repo/dspace/bitstream/10460/1502/7/Tec24_1_05.pdf
- 管野奈津美, 大杉豊、小林洋子「美術館における聴覚障害者を対象とした鑑賞支援と情報アクセシビリティ」『筑波技術大学テクノレポート』2017年, 24巻 (2) p.32-38
https://www.tsukuba-tech.ac.jp/repo/dspace/bitstream/10460/1559/6/Tec24_2_07.pdf - 社会福祉法人トット基金 日本ろう者劇団 育成×手話×芸術プロジェクト
https://townofsl2020.wixsite.com/tsa-deaf